久原本家グループは、「茅乃舎だし」「キャベツのうまたれ」「椒房庵のあごだし明太子」など、福岡から魅力的なヒット商品を発信し続けている創業128年の老舗企業。いかにして地方の醤油屋が、食品メーカーへと生まれ変わったのか。代表取締役社長の河邉哲司さんに、挑戦の歩みと成功の秘密をうかがいました。
始まりは、村人に愛された小さな醤油蔵
「久原本家グループ」の年商は、現在274億円(2021年2月期)。従業員は1300名を超える、福岡を代表する成長企業の本社は、福岡市の郊外にひろがる田園風景の真ん中にあります。創業者は久原村の初村長、河邉東介さん。村民たちの支えによって明治26年に開業された「久原醤油」が久原本家グループのルーツです。

創業者・河邉東介さんと久原村の人々
現在の社長・河邉哲司さんは4代目。しかし当初は、家業を継ぐつもりはなかったといいます。「食事が和食から洋食に変わっていくなかで、醤油屋では生きていけないと。無理やり継がされたというのが実情でした。しかし、継いだからには売り上げを上げたい。試行錯誤する日々が始まりました。」

河邉さんが入社した頃の醤油屋の営業は、地域の顧客を1軒1軒訪ねるスタイルでした。安定はしていたものの、新規開拓は難しく、そこへ、食事の洋風化、核家族化、そして、スーパーマーケットの台頭したことで、商売もだんだん下火になってきました。
「醤油だけではどうしようもない。」
その危機感から思いついたのが、納豆についたタレのような、醤油を原料にした小袋調味料の製造でした。さまざまな食品会社との取引が広がり業績は好転しましたが、下請けはいつ切られるかわかりません。
河邉さんは、その危機意識からドレッシングなどにも挑戦したものの、なかなかうまくいかなかったのだといいます。
「あきらめかけたときに思いついたのが、福岡の名物、明太子でした。百貨店やお土産コーナーにいけばたくさんの商品が販売されていましたが、ブランド力のある明太子屋は少ないと感じたのです。」
こうして誕生したのが『椒房庵(しょぼうあん)』でした。「椒房庵」の明太子の最大の特徴は国産の魚卵のみを使用しているところ。自社醸造の醤油とうまみ豊かな昆布だし、風味とうまみのバランスのとれた唐辛子で作った特製タレに付け込みました。
それでも、スタートして9年間は赤字続きだったといいます。「椒房庵」は原料にこだわっているぶん、原価が高く、そのうえ当時は福岡市の一等地にある百貨店「岩田屋」や空港で販売していたため、場所代が高かったのです。そこで、河邉さんは、本店を作り、定価で販売して利益を出すことを考えました。

久原本家 総本店。『茅乃舎』『椒房庵』流通向けブランド『くばら』など、久原本家グループの商品が豊富に揃い、郊外にありながら連日多くのお客様で賑わう
そしてもう1つの策が、通信販売でした。「お客様から電話で注文が入るようになったのです。福岡の岩田屋さんとか、空港店で販売しているので、明太子は、お土産やギフト用です。そのため、日本中に広めてもらえるし、おいしいと思ってもらえたら、電話が入るのです。」
こうした本店と通販の対策によって、10年目に黒字化。こうして、「椒房庵」で苦しんだ経験が、次の「茅乃舎」で役立つことになります。
「椒房庵」が軌道に乗ってきた平成11年、2つ目のヒット商品「キャベツのうまたれ」が生まれました。福岡の焼鳥屋に入ると、出てくるざっくり切ったキャベツ。各店に自家製のタレが用意されていますが、家庭用の市販品はありませんでした。そこで、自社の醤油を使って作ったところ大ヒット。「久原醤油」として自社ブランドを持てるようになりました。
しかし、河邉社長はこれだけでは危ない。3本目の矢を作る必要があると考えました。3本目を何にしようかと考えていく中で、今度は安心・安全の無添加が求められると確信。茅葺きの古民家でレストランを作り、スタートしたのが『茅乃舎(かやのや)』でした。

「御料理 茅乃舎」の手間暇をかけた料理はたちまち評判を呼び、レストランから生まれた商品「茅乃舎だし」も大ヒット。「茅乃舎ブランド」は同社の大きな柱へと成長します。

手軽に本格だしがとれると大人気の「茅乃舎だし」。これ一つでどんな料理も美味しく仕上がる
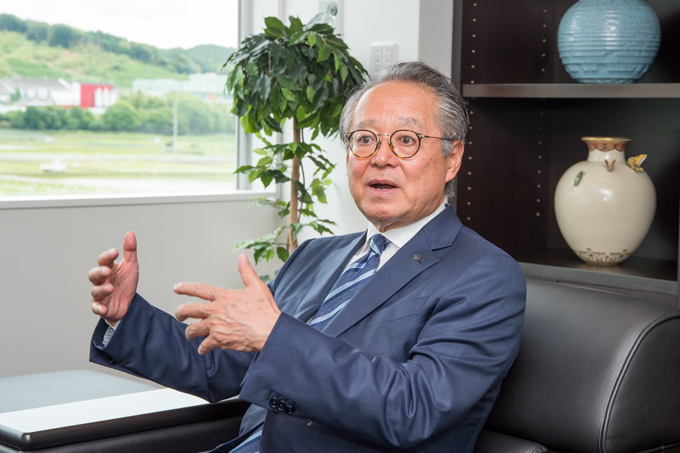
デザインへのこだわり
同社はパッケージにもこだわっており、社内に専任のデザイナーとコピーライターも抱えています。「社員が一緒に苦労しながら、作るときの思いも含めてデザイン化していくことが大事です。外注でさっと聞いて作るのと、本当に社員が心を込めてやるのとは全然違いますし、ブランド形成において大きな意味があったと思います。ブランドを作り、保つためには、逆にコストをかけなくてはなりません。」

地方企業だからできるビジネスモデル
「久原本家グループ」の売り上げの構成を見ると、大半を通販や直販といった、消費者とのダイレクトな取引が占めています。消費者とつながっているから、ニーズも直接聞くことができ、次の商品開発に活かすことができ、実際、そうして生まれた商品も数多くあるといいます。
「地方企業だからできるビジネスモデルだと思っています。田舎の小さな企業で、旧態依然とした醤油屋、酒屋でも、やりようによってはやれます。今は店舗を持たなくても、通信販売でお客さんへダイレクトに売ることができます。地方の中小企業が生き残れる時代になったのです。」
ただし、実際にアクションを起こせるかどうかは、また別な話。経営陣が「難しい」と判断すればそれで終わりで、挑戦してみないと道は拓けません。その決断力、行動力こそが、「久原本家グループ」の進化を導いてきたといっても過言ではないでしょう。
本物の調味料を使った、正しい日本食を世界へ届けたい
久原本家グループは、2016年からは海外進出にも挑戦し、ベトナム・ホーチミンに日本料理店を出店。アメリカには「茅乃舎オンラインショップUSA」を立ち上げました。

ベトナム・ホーチミンにオープンした日本料理店「KUBARA」

また、最近は国内の店舗でもインバウンドの売上が増えてきたといいます。
「特に東京駅とかミッドタウンとか新宿とかは、インバウンドのお客様が多い。そういう方々を取り込んでいくことで、海外での知名度が上がります。台湾では、台湾語で『茅乃舎』と呼んでいただけています。だしではなく、ブランドとして認知されているのです。」
その一方で気になっていることもあるのだそう。「和食人気の高まりに乗じて、中国や台湾などの企業が、日本のものに似せて作った調味料が出回っています。海外の人は、日本のものか、中国のものか、台湾のものかわかりません。だから、本物の調味料を使った、正しい日本食を広めたいと思っているのです。」

茅乃舎 東京ミッドタウン店
さすが!と言い続けられる企業を目指す
河邉さんは、ヒット商品を飛ばすたびに、期待値が上がっているのもひしひしと感じるといいます。「期待値が上がるのはきついですが、それを超えたとき、『さすが!』と言ってもらえます。我々は、『さすが!』と言い続けてもらえる企業でありたいと思います。そのためには、さまざまなことにチャレンジし続けなければなりません。」
「久原本家グループ」の今後の益々の発展が楽しみです。







