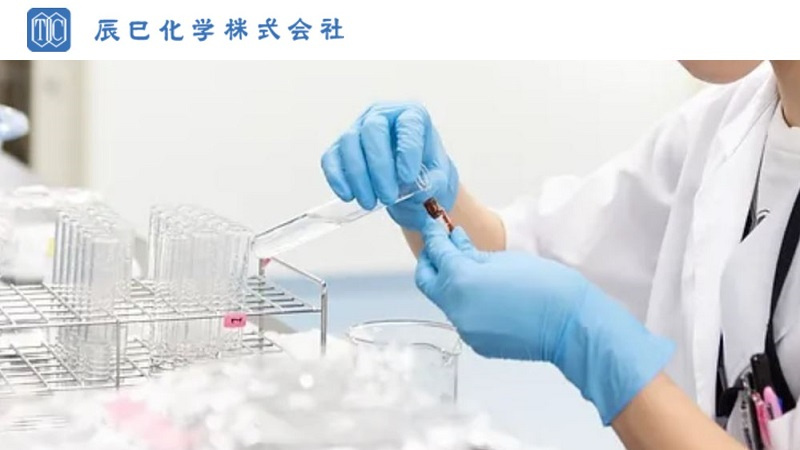コロナ禍によるリモートワークの普及により、都会での生活にこだわらず、地方で暮らす選択肢が広がっています。都会の喧騒を離れ、豊かな自然に囲まれながら、ゆとりのある有意義な人生を探求するライフスタイル。今でこそ、地方移住という言葉が珍しくなくなりましたが、コロナ禍よりも10年も前、東京の会社を辞めて日本の田舎を旅し、2013年5月より奥能登にご家族とともに移住した人がいます。それが、「田舎バックパッカー」の中川生馬さんです。リモートワークはまだ珍しく、地方移住のための支援もほとんど整っていなかった当時、世の中の先駆けとなる生き方を歩み始めた中川さんに迷いはなかったのでしょうか?そして、どのような想いで、地方移住を決断したのでしょうか。
10年の東京のキャリアを捨て、日本の田舎をめぐる旅へ

現在、能登半島にある石川県穴水町で家族と暮らす中川さんは、元々は東京で10年間、家と会社を往復するサラリーマンでした。大学卒業後、東京のITスタートアップ企業に就職。1年ほどで会社が買収されたことをきっかけに、大手PR会社に転職しました。主にIT系の企業を担当して5年ほど勤めながら、報道資料の作成やメディアとの折衝活動など、広報の実務的な部分はほぼすべて経験したのだと言います。
次は代理店ではなく、事業会社の“中”の広報業務を経験したいと、電機やエンターテインメントを中心に様々な事業を展開するグローバル企業にコーポレート広報として転職。海外出張も多くやりがいのある働きやすい会社で、仕事に不満は全くなく、がむしゃらに働いた中川さんでしたが、人生のほとんどを会社のために使う生き方に疑問を抱くようになります。
「かといって、独立するほどのスキルはないし、東京以外に広報の仕事のニーズがないのではと考えて決断できませんでした。悶々とした日々を過ごしましたね。子供の頃から将来は “サラリーマン”になるのが当たり前の教育を受けてきて、それ以外の生き方を知りませんでした。でも、有休を使って1週間ほど旅をして地方の人と仲良くなっても、すぐに帰る日が来てしまう。悩んだ末、会社生活に終止符を打って、2010年10月当時お付き合いしていた妻と一緒に日本の“田舎”を目指して旅に出ることにしたのです。」
当初は“田舎”と言えば“島”というイメージを持っていたため、離島ばかり訪れていた中川さんでしたが、旅を続けるうちに、中学生の頃に使っていた地図帳を持ち歩くようになります。「何気なく開いて目に入った知らない土地に行ってみるスタイルに変わりました。30キロくらいのバックパックにテントや寝袋、お米などの食料を入れて、ほぼ毎日テントで寝ていましたね。旅を始めて、1か月後の11月に結婚しましたが、就職せず、現在の住まいである能登に移住するまで約2年半、旅をしながら暮らしました。」


まだ珍しかった地方移住を実現
中川さんが2013年5月に移住することを決めた能登は、旅を始めて初めて訪れた場所でした。2年半も様々な日本の田舎を旅して、なぜ、能登への定住を決めたのでしょうか。
「移住後に仕事で上京する必要が生じたら、船便しかない離島は厳しい。かといって、そこそこ盛り上がっている土地は面白味がない気がします。首都圏と陸続きで交通の便がある程度あること。それでいながら、まだ世間に知られていない場所はどこか考えました。その条件に適合していたのが能登の穴水町でした。東京へのアクセスがよく、多くの人が名前も聞いたことがない土地。何よりも旅の最中に出会った穴水の人たちがとても魅力的でした。」
実をいうと、穴水町は人口がどんどん減少している地域。中川さんが移住する前、他の地域からの移住者は20年近く誰もいなかったのだと言います。現在も、奥能登で有名な輪島への移住者は少しずつ増えているものの、人口は減り続けています。「僕が2010年10月に来た時には人口が1万人強でしたが、現在は8千人を切っています。地方の人口減少が全国的に問題になっており、様々な対策はなされているかもしれません。しかし、現地で暮らす人たちは、共通して、結局、移住者が爆発的に増えて人口減少が大幅に改善されることはありえないと認識しているのです。」
しかし、そんなときでも中川さんの心は、田舎に眠る観光資源を発掘して、田舎の素晴らしさを世の中に発信したい想いで溢れていました。「田舎への旅」と「田舎でのライフスタイル」を軸にあらゆることに挑戦し、「田舎には仕事がない」という偏見を覆したい。そして、都市部の人たちに遊びに来てもらって、田舎を体験してもらいたい。
周囲に誰も自分と同じ移住者がいない穴水町で、中川さんはフリーランスとして、再び広報の仕事を始めることになるのです。
<後編:思い込みを捨てることで、生き方と働き方の可能性は大きく広がる>