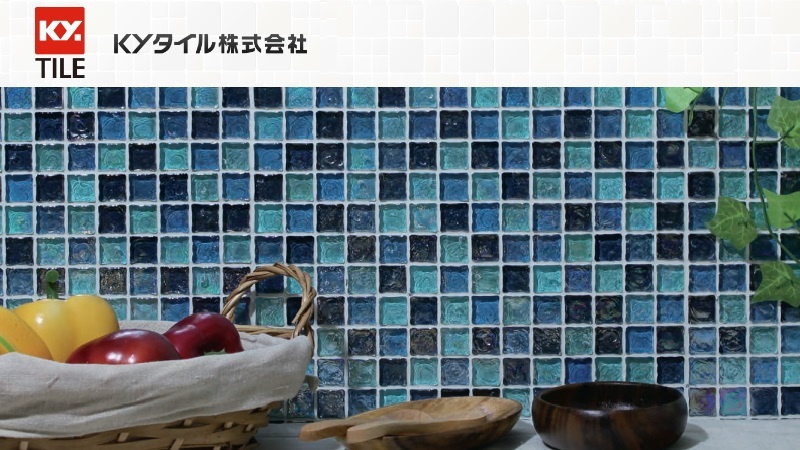自分自身の可能性を信じ逆境を乗り越え、 成功を掴んだアーティスト、俳優、クリエイター達。 時代の表現者達が語るSELF TURNとは? 彼らのストーリーを通じて、「自分らしい生き方、働き方」を考える。
2回目となる今回は、バンドARBとしてロックシーンの礎を築き、松田優作の意志を継ぎ俳優の道を切り開いた石橋凌さんに話を聞いた。
石橋凌流の「生きがい」「仕事論」とは?
幼少期、将来の夢は「映画評論家」
――まずは石橋さんの子どものころの話を聞かせてください。
「悪ガキでした(笑)。男ばかりの5人兄弟の末っ子なんですよ。だから夕飯時なんかは誰かが喧嘩をしてテーブルの周りを走り回ってて。その間におかずを食べるみたいなサバイバルな日々でしたね(笑)」
――『あしたのジョー』の世界ですね(笑)。子どものころの夢は?
「昭和30年代の中盤の九州の久留米っていう田舎にはまだ各家庭にテレビがないんですよ。ただ、歩いて10分ほどのところに映画館があって、そこに家族で行くのが楽しみだったんです。で、当時親父はパチンコ屋さんをやってたんですけど、僕が10歳を過ぎたころにそのパチンコ屋さんを辞めて会社員になったんです。サラリーマンはかなり大変そうで、そのさまを見ていたので俺はネクタイをしめて朝早く電車に乗ってゆられてっていう人生は絶対やめようってその当時決めたんです。で、中学生のとき、ホームルームで先生に『今日は君たちの将来の夢を語ってくれ』っていわれて『僕は映画評論家です』って答えたら、先生にひどく怒られましてね。でも、自分は真剣に、好きな映画を観て一生を送りたかったんですけどね」

人生の岐路 バンドマンか、イタリアンのコックか
――でも、先生からしたらふざけるなと?
「そんな夢みたいなこといいやがって!って感じでしたね。しかも…高校では音楽研究同好会に入りそこからはバンドマンとしての人生が始まったし(笑)。実際にアマチュアバンドでコンテストに出たり、博多にある『照和』っていう有名なライブハウスに高校2年から出始めていて、そのころには絶対プロになるって決めてましたから」

――で、そのままプロに?
「いや。同級生と先輩と組んでたバンドだったので高校3年になったときに進学、就職する人がでてきちゃって、バンドが自然消滅したんですね。でも、自分としては「ひとりでも曲をつくりながらまたメンバーを募って、いつか東京に行きたい」っていう夢があったわけです。だから、いろんなアルバイトをしながら夢を追っかけてました。最初はデパートのお中元・お歳暮の配達、ビルの窓拭き…で、最終的に落ち着いたのがイタリアンレストランの皿洗い。貼り紙で募集してて、そこに17歳で入って、結果19歳までそのお店にいましたね。その間にも東京からプロのお誘いが2回ほど来たんですよ。ところが『君、バンドじゃなくてソロで来なさい』っていわれて。『ソロじゃなくてどうしてもバンドやりたいんです』ってていよくお断りしてたら、東京からのお誘いはぱったりと来なくなって。で、そのイタリアンのマスターが『もうミュージシャンの道はあきらめて、うちで働きなさい』と。しかもイタリアで修業までさせてくれると。で、コックさんの道もいいのかなって思ってたいら福岡のKBCラジオのディレクターさんが電話をくれまして『東京で新しいバンドのオーディションがあるから受けてみないか?』って。その電話が運命の分かれ道でしたね」

「クビ」を覚悟で発信した自分らしさの表現
――それがARBのオーディションだったと?
「そうです。で、受かった。しかも、すごく恵まれた事務所だったんですよね。最初から合宿所と銘打って大きいマンションを与えられたり、楽器、楽器車、リハーサルスタジオもちゃんと準備されていて。仕事もメジャーな仕事がありましたから『ああ、いいなぁ』と思ってたんですが、最初のアルバムをつくるときに歌詞の中にひとことも社会的なこと、政治的なことは入れるなっていわれたんです。最初、耳を疑ったのね。『えっなんで?』って。だってこっちは小学生からずっとストーンズ、ビートルズ、ボブ・ディランとかを聴いてきて、そういう歌を日本語で歌おうと思っていたので。で、『じゃあ何を歌えばいいの?』って聞いたら『ラブソングを歌いなさい』っていわれたの。でも社会的・政治的な歌を思いきり歌ったんですよ(笑)」
――ハハハハ(笑)。
「歌ったらクビになっちゃったんですね。デビューして1年半でしたね。で、そこからの生活が本当に悲惨だった。マンションも楽器車も…全部没収ですから。しかも物価も九州から比べたら高くて…だからプロになってからですよ、質屋通いを覚えたのは(笑)。九州から持ってきてたレコードとか本を売って、それでリハーサルをやったりとかその日食べるものを買ったりして」

――気持ちは折れなかったんですか?
「当時、21、22歳だったんで、それが苦じゃなかったのね。後悔もなかったし、何より絶対見返してやろうっていう気持ちの方が強くて。で、ワンボックスカーを1台準備してそれで日本全国のライブハウスをドサまわりですよね」
音楽の壁からのキャリアチェンジ
――そこからARBは不死鳥のように蘇っていき、やがて武道館にまでたどり着いたのに、今度は石橋さん自身がARBをとめてしまうわけですが……。
「ライブハウスで日本全国ドサまわりして、段々とホールでやれるようになっていくころには、ワンボックスカーじゃなくて移動が新幹線とか飛行機になってましたね。でも、僕はお茶の間に入っていきたかったんです、ビートルズやストーンズのように。ですが、僕らはお茶の間にいけず、そのジレンマはずっとつきまとってて。それまでもいろんな壁を自分たちなりに乗り越えてきてたんですけど…。このときは27歳。しかもそれまでの壁とは違ってもっとぶ厚くて高い壁だったんですよね。で、もうここまでだなって思ったんです。自分が思うロックミュージックはここまで、もうやりきったっていう。もうこれ以上どうやろうが、たぶんもう切り崩せないなって思ってしまって音楽を辞めて九州に帰ろうかなって。ほかの仕事を探すぐらいまで落ち込んでたんですよ」
――ええ。
「で、そのときに松田優作さんと出逢って。優作さんにその悩みを全部話したんです。そしたら、『やり続けるしかないんだよ。でも、大事にひとつひとつ手を抜かずにやっていればどっかでそれをちゃんと見てる人がいると思う。だからその人が近づいてきたときに弾ければいいんじゃないか』って。で、その次に『ただお前がいる音楽の世界よりも俺がいる映画の世界のほうがメディアとして大きいから、映画で名前と顔を売ったらどう?』っていってくれたんですね。で、それから少しして優作さんが監督の映画『ア・ホーマンス』に役者として呼ばれて。台本渡されて『これお前やってみろ』っていわれたときに、殴られる覚悟で『優作さん、これ、バンドを茶の間に売るための宣伝でいいですか?』っていっちゃったの。そしたら…2、3秒、間があったんですよ。わぁーこれはパンチがくるなぁと思ってたら、ニヤッと笑って『それでいいよ』と。で、役者デビューしたんです。その映画のおかげで音楽に対するモヤモヤも消えて、僕は音楽の世界に戻ったんですが、そのあと、優作さんが亡くなられてしまい…」
――89年の出来事でしたね。
「ええ。で、優作さんの意志を継いでいきたいと思ったんです。優作さんは『ブラックレイン』で出た経験から日本人の俳優もアメリカの映画俳優組合(SAG)に入り、アメリカ映画で対等に演技をするようにならないとダメだと考えていて。ただ僕はそのとき34歳でしたから、俳優と音楽の両方やってたらそこまでいけないなと思ったんで一旦音楽を封印して、俳優としてやれるところまでやろうと。で、34歳から、本当にいろんな恥をかきながら7年かかって95年にSAGに入れたんです。それで、天国にいる優作さんには『ここまでいけました』って報告して、97年から音楽活動も再開したんですね」

意思を曲げすに生きてきた石橋さんの生きがいを感じる瞬間とは
――なるほど。そんな意思を曲げずに生きてきた石橋さんが、生きがいを感じる瞬間って?
「小さいときから観ていた、たとえば『イージー・ライダー』や『シャイニング』のジャック・ニコルソンと2人だけのシーンができたり、音楽の世界でいうとロックンロールの生みの親といわれているチャック・ベリーと同じステージに立てたり。そんな瞬間は生きがいを感じたし、本物と一緒にできたのは僕の財産ですよね。でも自分が本物にならないといけないと思うんですよ。憧れだけじゃなくて」
――もう本物になってると思うんですけど。しかしここまでこれたのは石橋さんが筋を通して来たのも大きいのかなぁと思いますが……。
「生き方としては不器用なのかもしれないんですけど、時間はかかっても筋は通したかった。自分がこうだと思ったら、人にどう誤解されようがそこにはいきたいんですよ。それはときとして非常に孤独な作業というか、人との縁を切ってまでもそこにいかなきゃいけないんじゃないかなっていう考えなんで」

俳優 石橋凌にとっての仕事とは
――さて、最後の質問です。石橋さんにとって、仕事とは?
「仕事とはやっぱり〈生きる〉ってことじゃないですかね。仕事がなければ食えないわけですから。質問の答えからずれるかもしれませんが、81年にARBの3枚目のアルバム『ボーイズ&ガールズ』を出したきっかけは京都にある磔磔(たくたく)っていうライブハウスでの出来事で、その磔磔でのライブが終わった瞬間にオーディエンスの若い男の子・女の子たちが楽屋になだれ込んで入ってきたんです。で、開口一番みんなが『凌、バンドって儲かるのか?』って。『え? なんで?』って聞いたら『私たちもバンドやろうと思ってる』と。なかにはカメラマンになりたい子もいたり、レコードジャケットのデザイナーになりたい子もいたりで。そのときに『これだけいろんな夢をもった人たちが出てくれば日本も変わるんじゃないかな』って思ったの。というのも僕らが高校生のときにプロのミュージシャンになりたいっていったら、学校からえらく怒られたもんです。しかも当時は二者選択、大学に進学するかサラリーマンになるかの時代。でも、その磔磔の楽屋では、自分が本当に好きな仕事をもって、それを死ぬまでやっていくんだっていう構想をもってる人たちが出てきたわけで。それで『日本よ、変わってくれ!』っていう想いで『ボーイズ&ガールズ』っていう曲をつくったんですよ。“大いなる個”っていう言葉があるように、自分個人の考え、自分個人の夢、仕事をもった人がいっぱい出てくると、面白い社会になるんでね」

――そういう“個”が集まった社会は豊かな多様性のある社会ですよね。
「そう。それが豊かなんですよね。大きな会社に勤めてサラリーもらって退職金があってっていうのは物理的には安定しているのかもしれない。でも、そういうことじゃなくて本当の意味での豊かさ。精神的なもの・気持ちの豊かさをそろそろもったほうがいいんじゃないかなと思いますよ」
――そう思います。
「だからこのサイトを見ている人には、大いなる“個”になってください、といいたいです。でもそれは、自分のことの“個”、つまり利己主義になれってことじゃなくて。自分がちゃんとあれば人のこともちゃんと見えて、人のことも慮(おもんばか)れる人になれると思うんですよ」
――出世競争に明け暮れていたら他人のことを慮れないですもんね。
「サラリーマンの多くが、上司からいわれ下から突きあげられる現実じゃないですか。しかも、 それがかなり切羽詰まっている環境だと思うんですよ。なので、まずは大いなる“個”としてそこから抜け出す勇気をもってほしいですね。そしたら、自分も豊かになれて人にも優しくなれますから」


石橋 凌
1956 年7月20日生まれ / 福岡県久留米市出身 / 血液型 AB
伝説的ロックバンドA.R.B.(エーアールビー)の元VOCAL として知られる石橋凌。A.R.B は1977 年結成され、シングル「野良犬」で1978年にデビュー。1990 年に松田優作の意思を継ぐべく、役者としての活動に専念する意思を固めた石橋凌の強い意志により活動停止。1990年 代々木体育館での活動休止ライブでは 2 万人動員。1998 年に新メンバーにより復活。(ユニコーンEBI がBASS として加入。)1998年 AL「REAL LIFE」リリース。セールス10 万枚を超える。1999年1 月24日 武道館にて1万人動員。2006年3 月、ファンへ最後のメッセージ「一生歌っていきます。魂こがして」と残し石橋凌はA.R.B を脱退、それにより A.R.B は解散。A.R.Bの強い信念を持った音楽は氷室京介、福山雅治、ユニコーン、奥田民生, EBI ( 復活時BASS として加入) JUN SKY WALKER(S)、THE HIGH-LOWS 甲本ヒロト、 真島昌利など数多くのミュージシャンに影響を与えた。役者としても、映画やドラマに数多く出演。三池崇史監督や北野武監督作品、ハリウッド作品にも出演している。シンガ ーと俳優 2つの顔を持つ石橋凌が2011年、一人の表現者として音楽活動を再開する。最新作はAL「may Burn!」(2017-07-19発売)