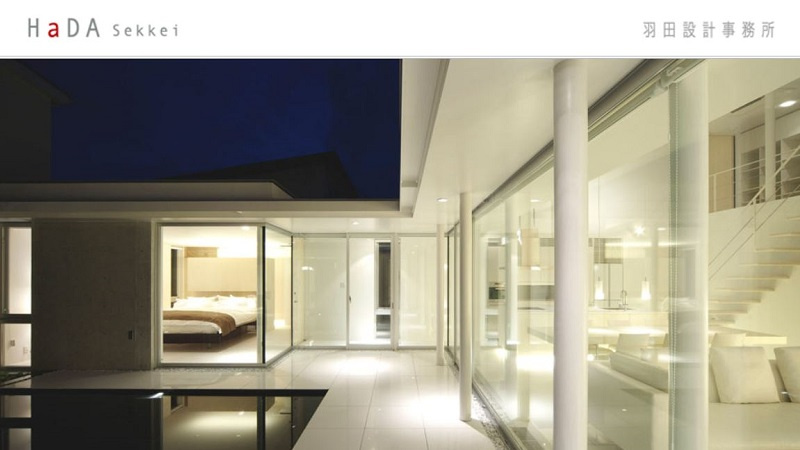まだ日本人が海外で活躍する事が希だった1970年代、一人の写真家が海を越えた。デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、ジム・ジャームッシュ、YMO、忌野清志郎、布袋寅泰、MIYAVI…国境も世代も越えてアーティストから愛され、“世界のSUKITA”の異名を持つ写真家・鋤田正義。
80歳を迎えるいまでもカメラを持ち、精力的に写真を撮り続けている。
その鋤田の仕事論に迫った。
カメラとの出会い
――カメラ、写真に興味を持たれたきっかけは?
「初めてカメラを持ったのは高校時代、西暦でいうと1956年ですね。で、そのときに撮った1枚が、夏祭りで“祭り傘”を被り縁側に座る母親の写真なんです。よく『自身の作品の中でのベストショットは?』と聞かれることがあるのですが、最初に撮ったその写真を挙げるんです」

――ファーストショットがベストショットだったということですね?
「はい。ただし、撮っているとき、自分が写真家という意識は別にないですよね。どこにでもいる高校生のガキがカメラを買ってもらって、それで写真を撮っただけなんで。じゃあなんでカメラに興味を持ったかというと、時代背景があったと思います。僕が高校のときって戦後間もないころで、戦争に負けてアメリカから映画や音楽といった文化がどーっと押し寄せて、その波に巻き込まれているような感じだったんです。あとは、おばあちゃんが映画好きで、小学生の頃からよく映画館には連れてってもらっていて、その頃から映画や映像に興味を持っていましたね」
――なるほど。映画から写真へ?
「写真雑誌はもうすでに世の中にあったので、立ち読みはしてました。お金はないから買えなかったですけど(笑)。親父も戦死して家計が苦しかったんですが、リコーフレックスという薄い二眼レフのカメラが安く大量に出回っていてそれを買ってもらえたんです。それを手にしたときからですね、カメラ、写真にのめり込んだのは」
広告代理店を辞め、フリーカメラマンとなった背景
――高校を卒業した後は写真学校に行かれて、その後に広告代理店に勤めたのがプロとしての第一歩でしょうか?
「そうですね。写真学校時代に写真家の土門拳さんらと触れ合う機会があり、商業的な写真を撮ることよりも、作品を発表する写真家に憧れたんですが、親からは「それでは食べていけない」っていわれたり、町に写真館がどんどん出来ていたタイミングで、要は戦後の発展が始まっていたので、その時代のレールに乗った感じで、広告代理店に就職しました。その広告代理店での広告で写真を撮ることは要するにメジャーでの仕事だったので、自分の中ですごく勉強になりました」
――その広告代理店を辞めてフリーになったのは何故ですか?
「会社に不満はなかったんです。でも、外からの仕事の依頼が多くなってきて、別のところから収入を得るのが増えてきてたんです。なんだか会社の連中に悪いよなって思うようになってきたので。それで会社を辞めてフリーになったんです。時はちょうどウッドストック時代だったんで、とりあえずニューヨークに行きました。そこでヴェルヴェット・アンダーグラウンドのライヴを観たり、CBGBというライヴハウスに行ったりしていたら、オフ・オフ・ブロードウェイで寺山修司さんとも知り合い、寺山作品の写真を撮らせてもらうようになりました」
――そうだったんですね。それにしても広告代理店を辞めるときに不安はなかったんですか?
「不安はなかったですね。戦後の人間ですから、物食えないのは当たり前なんで(笑)」

既成の考え方にとらわれない、フラットな状態がもつ力
――写真家として決定的な成功を収めたのが1977年のデヴィッド・ボウイのアルバム『ヒーローズ』のジャケット写真だと思いますが、そのときの撮影はどんな様子でしたか?
「あの撮影の前に、僕は何度かロンドンでボウイを撮っているんですが、1977年の撮影のときはボウイはイギー・ポップと一緒にプロモーションで日本に来ていたんです。つまり、ワールド・ツアーで来てないので、本人たちの緊張感が違ったんですよ」
――ライヴツアーじゃなかったのでリラックスした状態で撮れたと?
「そうです。しかもボウイは座長みたいなものなので、もしワールド・ツアーで来ていたら、バンドのメンバーやスタッフみんなを意識しておかなきゃダメなので、頭の中にフォト・セッションをするという考えがないんです。なので、ツアーでの来日だったら、フォト・セッションをお願いしても絶対に受けないでしょうね。でもこのときはプロモーションだったので受けてくれたし、すごくリラックスしていました。
――いくらボウイがリラックスをしてたといっても、誰が撮ってもいい写真になるわけではないはずです
「77年ってちょうどロンドン・パンクの全盛期だったんです。僕もロンドンに行ってパンクを撮っていました。その同じ年にボウイが日本に来たので、ロンドンに暮らす若者達が感じている空気はなんとなくわかっていて。ボウイからの依頼で、スタイリストに衣装として革ジャンだけを注文していました。ボウイはその革ジャンを普段着にそのまま重ねてくれたんです。普通、これくらいのタレントの撮影となれば、スラックスから靴まで変えますから。でも、このときは革ジャン以外は普段着のままで、これはあんまり人に言ってないんですけど、彼が履いているコーデュロイ・パンツ、東京滞在中ずっと履いていたのでだいぶ擦り切れていて、それも一連の写真に写っています」

――よくそんな状態をボウイは撮らせてくれましたよね
「それくらい向こうが変わろうとしている空気が読めたんです。そしてその背景にはパンクの時代があったし、革ジャンを着た時点でそういうパンクなモードになったんだと思います。だから、途中で髪が乱れようがボウイは一切気にしてなかったんです。普通、タレントって髪の一本一本まで気にするものです。でも全然気にしてないどころか、髪をクシャクシャにしたり、タバコを吸ったり。そういうのも全部撮りました。だからロールチェンジが大変でしたね。12枚撮ったらフィルムロール1本終わりなんで、カメラを2?3台用意してカメラごととっかえひっかえしながら撮りました。それで、このときに教わりましたね、ポートレートっていうのはこういうこともあるんだってことを。相手は生き物なわけで、自分の写真家としてのスタイルなんて簡単にぶっ飛ぶんです。こうして撮ったら上手い写真が撮れるとか、そういう技術の積み重ねって本当はいらないんだなって。それこそパンクの考え方じゃないけど、既成のもの、既成の考え方がどうでもよくなってしまいました。フラットな状態に自分をおいておいた方が受け入れやすいんだって思いました。逆に頑固に自分のスタイルを持っていると、受け入れられないですから」
――そういう写真哲学を77年のボウイとのフォト・セッションから学んだんですね
「おこがましいことをいえば、ボウイもこの写真をきっかけに変わったのかなぁとは思います。彼がこの写真をアルバム『ヒーローズ』のジャケットに使いたかった意味を感じるんです。ボウイは、それまでジギー・スターダストでカリスマ的な美意識でやっていた部分と全部オサラバして、一から新しいものをつくるためにドイツ・ベルリンに行くわけです。そして、『ロウ』『ヒーローズ』『ロジャー』の所謂ベルリン3部作を完成させた。そのちょうど過渡期だったんですよね」

最終目標は“世界のSUKITA”ではない!?
――そして、鋤田さん自身も『世界のSUKITA』と呼ばれていくわけです
「でも“世界のSUKITA”を目指してるわけじゃなくて、自分の写真が世界中で愛されることが最終目的なんだろうと思うんです。もちろん、広告代理店にいたから頭の回路のどこかでは有名なものを撮れたら自分も有名になるみたいな算段は自然にこびりついているとは思います(笑)。でもそんなものは、渡世術の予備みたいなもので、本質的なものとは思ってないです」
――鋤田さんが無名のお母さまの写真をベスト・ショットに挙げるのもそこなのかなぁと思うんです。インタビューも同じで、どんなに言葉がつまらなくても有名だったら、インタビューの企画は通ります。逆にどんなに言葉が鋭くても無名だと企画は通りません。そういう数字主義へのアンチテーゼにも、自分への戒めにも思えます
「ボウイとは40数年間付き合いがありましたけど、ベッタリな関係ではないんですよ。僕は東洋の日本にいて彼らはイギリスかアメリカにいるわけで、普段から会話をする機会もないです。日本に来たときも、僕が撮影で行くときも、僕は英語ができないから、面と向かって彼の考えていることを尋ねることもないですし。彼と僕の関係は、カメラがあって、その向こうにボウイがいて、こっちに僕がいる。大雑把にいえばそれだけですよ。そういうフラットな関係でしかなくて、撮影をしているときに有名も無名も関係ないんです」
――鋤田さんのことを追ったドキュメンタリー映画『SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬』の中で、糸井さんが鋤田さんのことを「こんなにやわらかくて強い人はいない」といっていましたが、お話を伺っていると、写真を撮る姿勢が本当にしなやかですよね。その最たる例がデジタル撮影への対応です。戦後すぐ生まれの鋤田さんですが、普通にデジタルで撮影をしていますね
「YMOをデビューからずっと撮っていたのですが、レコーディングの最中、細野さんも含めみんなインベーダーゲームにはまっていたんですよ。それこそ当時、糸井さんも一緒に、原宿セントラルアパートの喫茶店レオンで競ってインベーダーゲームをやってました。でもあるとき知人から『なんでそんな生産性のないことに夢中になるの?』っていわれて(笑)。確かにそうだなぁと思って、それでインベーダーゲームは辞めたんです。カメラは新しいのが出てきたら仕方なく新しいのを追ってますけど、インベーダーゲームの教訓からPCの類に近づかないようにしてたのが間違いで、いまだにPCが全然わからないんです。なので、PCに関してはアシスタントさんにやってもらっています」
――鋤田さんクラスの写真家ともなれば、『俺はフィルムでしか撮らないぞ』という選択肢もあったと思うのですが?
「新しい機械の面白さは、自分の中で遊び心としてあるんですよね」
――映画『SUKITA』の中でもどなたかが『鋤田さんは良い意味でミーハー』とおっしゃっていましたが、まさにそういうことですね
「そういうミーハーな部分はあります。それでいて機械はどうでもいいってとこもあるんですよ。カメラは別にライカじゃなくてもいいです。安いカメラでもなんでもいいです。だからスマホで撮ってそれで写真をつくるのもいいんじゃない?って思います。それくらいの柔らかい考えはもっています。むしろそういう中から将来すごい人が出てくるような気がするんです。写真家の鎧を着ないでどんどん撮れちゃうわけでしょ?」
――はい。では、みんなが携帯でバシャバシャ撮って表現するのは鋤田さん的には嫌じゃないんですか?
「嫌じゃないですよ。むしろそういう写真の中から凄い作品が出てきそうな気がする。だって四六時中誰かが写真を撮ってるわけですよね? その中の一人くらい凄い人が出てきてもいいと思いますけどね」

――柔らかいですね。最後に「鋤田さんにとって仕事とは?」というのを聞こうと思っているんですけど、そもそも写真は仕事ではない感じですよね?
「その通りです(笑)。仕事という意識はないです」
自分が一度出した答えや、人生の選択にしがみついていても意味がない。大事なのは遊び心
――では『仕事とは?』と聞かれたらなんて答えますか?
「僕の仕事っていままでCMの仕事のほうが作品をつくるのより多かったんです。で、そのときにいつも〝遊び心〟は絶対もっておかないと、と思っています。でもそれがいいのか悪いのかは、いまだにわからないですけどね。僕は答えはあんまり出さない方です。疑問はいろいろもつけど、答えは死ぬ直前でいいのかなと思っちゃうんです(笑)」
――疑問はもつけど答えは出さない?
「だって、答えなんて、出ないでしょうから」
――出ないですね
「出ても、その答えも変わっていくんですよ。だから自分が一度出した答えや、人生の選択にしがみついていても意味ないと思います。大事なのは遊び心です」


鋤田 正義(すきた まさよし)
【ドキュメンタリー映画】
『SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬』
デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、マーク・ボラン、YMO、寺山修司、忌野清志郎…時代を駆け抜けた天才たちの≪永遠の時≫を獲得した写真家・鋤田正義(SUKITA)に迫る、初のドキュメンタリー!
公式HP: http://sukita-movie.com/index.php
【Profile】
1938年、福岡生まれ。
1960年代から頭角を現し、1970年代には活動の場を世界に広げる。デヴィッド・ボウイやイギー・ポップ、マーク・ボラン、忌野清志郎、YMO等の写真が有名だが、そのフィールドは広告、ファッション、音楽、映画まで多岐にわたる。2012年、40年間撮り続けてきたデヴィッド・ボウイの写真集『BOWIE×SUKITA Speed of Life 生命の速度』をイギリスから出版。その他の写真集にボウイ『氣』、『T.REX 1972』、『YMO×SUKITA』、『SOUL 忌野清志郎』等がある。またイギリス、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカ、オーストラリア等の世界各地で自身の写真展を展開中。