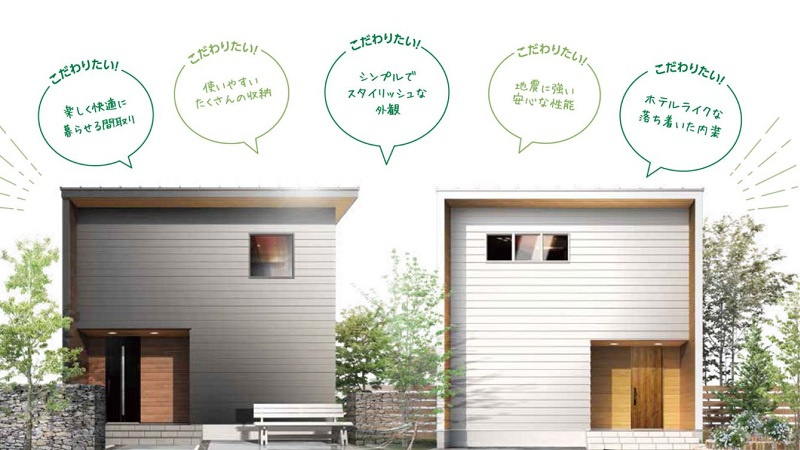琵琶湖のほとりに位置するバラ農園「Rose Farm KEIJI」では、幾重にも折り重なる丸みをおびた花弁をもつ、美しい「和ばら」を見ることができます。世界で唯一のバラブランド「和ばら」を生んだのはバラ作家の國枝啓司さん。そして「和ばら」の価値を高め、フラワービジネスとして確立させたのが、啓司さんの長男、健一さんです。健一さんはどのようにして、「和ばら」のブランド化を成功させたのでしょうか。
生まれ育った守山市にUターン。父のバラをビジネスに

滋賀県守山市に位置する「Rose Farm KEIJI」は、3代続くバラ農家である國枝家の農園のひとつです。
國枝家の次男、國枝啓司さんの長男、健一さんは、バラの生産の様子を見ながら成長しました。
しかし、健一さんには、農園を継ぐ意思はありませんでした。父親の啓司さんから農場を継がなくてもよいと言われていましたし、実は啓司さん自身も自分の代でバラづくりをやめるつもりだったのだといいます。
東京の大学を卒業後、一般企業に就職した健一さんでしたが、2006年、守山市にUターンすることになります。仕事をしているうちに、生まれ育った守山市で起業したいと思うようになったのです。
人が純粋に美しいと思うものを突き詰めたい

健一さんがビジネスのコンテンツとして選んだのは、父親の啓司さんが趣味で育苗していたオリジナルのバラでした。
ビジネスの成功に必要なのは、「社会にとって価値があるものを創造すること」と「この世にないものをつくること」。健一さんは、この2つをバラというコンテンツによって実現したいと考えたのだといいます。
「人がバラを見たとき、飾りたいと思う衝動に理屈はありません。人が純粋に美しいと思えるものの価値を突き詰めたいと思いました。それに、バラの原種は世界各国に存在します。種類が豊富で、変化に富んでいることも、バラをビジネスにするモチベーションになりました。」
健一さんが守山市に戻り、最初にとりかかったのが切り花業界の流通状況の把握でした。ほとんどの生産者は自分たちで値段を設定せず、流通業者に花の販売を委託するため、流通業者に生産者が依存する構図が生まれます。流通業者の立場が強くなることで、日持ちがする花や、流通上扱いやすい、流通業者に都合のよい花を生産させられるようになり、顧客の満足度をふまえた花づくりから遠ざかってしまうのだと健一さんはいいます。
生産者はつくったら終わりで、買い手の顔を見ることがありません。「花を買った人々がどんな表情をしているかを生産者が知らない点に、ビジネスの可能性を感じました。」
親子の夢を叶える和ばら

啓司さんは、ヨーロッパをはじめ、世界中の様々な品種をかけあわせることで、オリジナルの品種開発に成功。健一さんが「日本から発信する新しいバラの形」という意味を込めて「和ばら」と名づけました。
健一さんは大学時代ドイツへ留学し、「いつか海外で通用する力を付けること」を決心して帰国しました。そして父親の啓司さんにも、いつか自分のバラを世界中の花屋さんで売る夢がありました。まさに、2人の夢を叶えようとしているのが「和ばら」だったのです。

健一さんは「和ばら」の価値を理解してくれる人々へアプローチしていくことを決意し、独学でホームページを制作して、和ばらの認知度を高めるために試行錯誤を続けます。
「独自で育苗するバラは出荷量が少なく「和ばら」の名は、なかなか知れ渡りませんでした。そこで、東京にも出荷の窓口を広げてみたのです。すると、和ばらのビジュアルがフラワーアーティストの目にとまり、少しずつ注目をされるようになったのです。」

メディアでも取り上げられたことも手伝って、和ばらは大きな反響を呼びました。
和ばらは世界へ
和ばらには、色や形、香りで「美咲」「雅」「つむぎ」など、さまざまな種類があります。健一さんは「和ばら」の海外市場への展開や加工商品の企画、新商品を開発・販売など、育種からPR、販売までトータルでプロデュースしています。
育種者自身が商品をブランディングすることは、切り花業界では稀なこと。業界の常識を覆して実現できたのは、健一さんが園芸や農業を学んだことが一度もない素人で、切り花業界の固定概念にとらわれることなかったからだといいます。
現在、親子二人三脚で育んできた和ばらは、健一さんたちの花への情熱に共感する世界各国のパートナーファームで栽培されています。
これからも続く、親子の切り花ビジネス。世界へ向けてのさらなる発展が楽しみです。