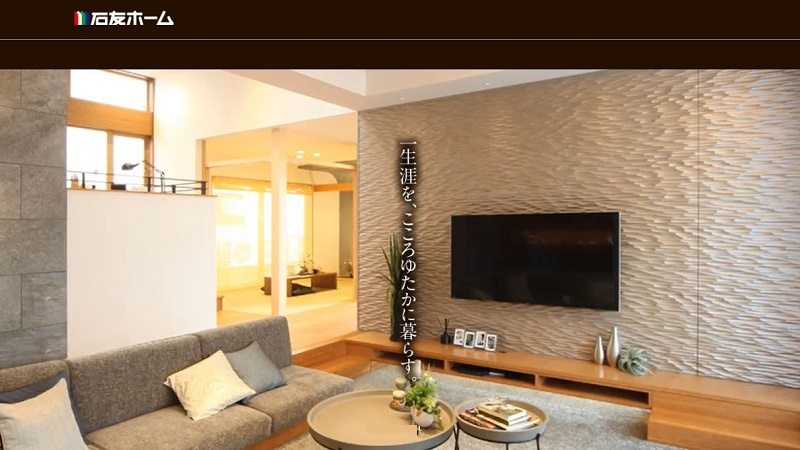滋賀県守山市で誕生した「和ばら」は、世界で一つだけのバラのブランドです。この「和ばら」をブランド商品にまで押し上げ、フラワービジネスとして確立させたのが、滋賀県守山市在住の國枝健一さん。和ばら作家として活躍する父親の國枝啓司さんとともに、二人三脚で歩んできた「和ばら」ブランド化の道のりを伺いました。
奥ゆかしく、愛らしい「和ばら」
滋賀県守山市。日本一の大きさをほこる湖・琵琶湖のほとりに、バラ農園「Rose Farm KEIJI」があります。ここはバラ農家として3代続く國枝家の農園のひとつで、國枝家の次男であり、バラ作家である國枝啓司さんの活動拠点。そして、啓司さんの長男・健一さんのオフィスでもあります。

「和ばら」とは、世界中でここにしかないブランドであり、Rose Farm KEIJIのオリジナル品種。ヨーロッパをはじめ、世界中の様々な品種をかけあわせることで、啓司さん独自の品種を生み出しました。
その姿は、ダイナミックで気品あふれる姿とは違い、繊細な花弁が幾重にも折り重なった丸みのある形と、優しい香りが特長。例えるなら、ヨーロッパのバラが威風堂々たる女王だとすれば、「和ばら」は十二単をまとったお姫様。奥ゆかしい、愛らしい、といった言葉がぴったり合います。

いまでこそ「和ばら」をブランドとして売り出していますが、かつては啓司さんが趣味で育てていたに過ぎませんでした。それもたったの2、3種。というのも、啓司さんは自分の代でバラの生産をやめるつもりだったのだとか。まさに終わろうとしていた家業が、20年、30年先を見据えて成長し始めている。その陰には、息子・健一さんの活躍がありました。
家業とは無縁の会社員時代を経て起業
バラ農家の長男として生まれた健一さんは、父親が行うバラの生産や育種を身近に感じながら成長。静岡の高校、そして東京の大学を卒業後、大手メーカーの子会社へ就職しました。
会社員時代は、様々な企業で働く海外駐在員をサポート。大学時代にドイツへ留学していたこともあり、海外と接点のある仕事を求めてこの会社に決めたのだとか。このころ、彼にはバラ農家を継ぐ意志はありませんでした。というのも、両親から「家業は継がなくていい」と聞かされていたこと、そして、父親の啓司さんが次男のため、家業を本家が継ぐことがわかっていたからだそう。
そんななか、東京で仕事に携わるうちに起業への思いが強くなり、実家に戻って生まれ育った町で起業することを決意。そのとき、起業のコンテンツに決めていたのは「生産者と花を手にした人の笑顔を結びつける」ことでした。

幼い頃から家業を側で見てきた健一さんが、かねてから感じていたことは「生産者は生産や出荷がメインで、バラを買う人の顔を知るすべがなかった」ということ。一方で自身の会社員時代には、友人やクライアントへ花を贈ったときに喜びを感じたり、花を贈られた人の笑顔が印象に残ったりしていた、といいます。
この2つの経験から健一さんは、花を買った人々がどんな表情をしているか、どんな気持ちでいるかを生産者自身が知らずにいるという点に、まだ開拓されていない新たなビジネスの可能性があるはずだ、と考えました。
さらにこれから家業を続けていくにあたり「継続的な事業を行うために何かの強みも必要」と、実家の父が育種しているオリジナルのバラを価値化していくこともビジネスの核とすることにしました。
國枝家をとりまく、切り花業界の現状と課題
2006年、健一さんは会社を退職し、守山市にUターン。そして、最初にとりかかったのは、販売と密接に関係する切り花業界の流通の把握でした。
健一さんが自ら各所を見て回ったところ、ほとんどの生産者が、出荷する花を流通業者へ委託販売する傾向にあることを知ります。生産者はコストをかけて出荷しているにも関わらず、自分たちで値段を設定することなく、業者に一任しているのだそう。このような関係性は、委託販売を任されている流通業者が強者になりがちで、その業者に生産者が依存してしまいます。
しかし固定の値段を設定しなくても、その価格で売れるように戦略を立てたり、商品価値を上げるために業者と交渉したりすることは可能。これらの戦略や交渉を生産者があえて行ってこなかったのは、花を出荷していれば、それなりに生活できるレベルで取引される時代が長く続いていたからです。
「本来生産者は、自分たちが何を目標にして生産し、どういった顧客に届けるか。そのために価格をいくらに設定するかの目標や指針があるはず。でもいまのままでは“つくったら終わり”。どんな人が買ってくれるかが見えていないんですよね」と健一さん。
また流通業者が強い立場にあると、業者の価値基準でマーケット全体が形づくられるため、様々な価値が生み出されにくくなっていた、とも話します。
「顧客の消費行動や満足度をふまえた花づくりではなく、日持ちがするもの、流通上扱い易いものといった、流通業者に向けた花を栽培・生産させるのが当たり前になっていました」
健一さんは、このポイントも「生産者と買い手が結びつかない原因」だということに気が付きました。
市場が求める商品ではなく、社会にとって価値のあるものを
健一さんがビジネスで成功するために常に考えていることは、「社会にとって価値があるものを創造すること」、そして「いままだこの世にないものをつくること」。この2つをバラというコンテンツを使って実現したいと思うようになりました。
「花は人類がこの世に生まれたときから変わることなく愛され続けてきた存在。その普遍的な価値がバラにはあるんじゃないか。たとえばバラを庭園や店先で見かけたとき、“部屋に飾りたい”と思ったときの衝動は、人の根源にある理屈ぬきの感情ですよね。私たちが純粋に美しいと思えるものの価値を突き詰め、訴求していきたいと思いました。そして、それが父が手掛けていたオリジナルのバラだと確信したんです」
ところで健一さんが花の中でもバラに注目している背景には、世界各地にバラの原種が存在し、個人・企業関係なく自由に品種を開発することができること、バラが世界的に花の象徴的な存在でありながら、色や形、香りなど種類が豊富で、変化に富んでいることが挙げられます。
家業で手掛けていた品種がバラだったという幸運が重なり、健一さんは自信をもってバラで勝負ができたというわけです。
父と子の夢が託された「和ばら」の誕生
父親のオリジナル品種のバラを「和ばら」と命名した健一さん。この名前を付けた背景には、父と子の夢が原点にあるといいます。

健一さんはドイツへ留学していた頃、現地で仕事を得るチャンスがあったそう。しかし日本人が海外で働くには、現地で必要とされるスキルなどが必要と思いとどまり、「いつか海外で通用する力を付けること」を決心し、帰国します。
そして父親の啓司さんは、いまから36年前にフランスやオランダ、ドイツなどで育種を開始。そのときの経験から、いつか自分のバラを世界中の花屋さんで売りたい、という夢がありました。
「世界を舞台に活躍したい」という2人の夢を叶えるのが、父親が生み出す「ばら」だと確信した健一さんは、これからの事業の世界展開を見据え、「日本から発信する新しいバラの形」という意味を込めて「和ばら」と名付けたのです。
こうして健一さんは流通然とした花ではなく、美意識を突き詰めてつくられる「和ばら」への情熱や生産背景も含め、価値を理解してくれる人々へアプローチしていくことを決めました。
東京で反響を呼び、知名度アップ
「和ばら」の誕生後、健一さんはまずホームページを制作することにしました。これは一般客の問い合わせに対応する受け皿の役割と、和ばらの広報を兼ねており、認知度を向上させ需要を生み出すには最も重要なポイントの一つです。健一さんはホームページ制作をゼロから独学でマスターし、制作・更新全てを自身で担当したのだそう。
また、「和ばら」と名付けた当初は大阪へ出荷していたものの、その知名度は乏しいものでした。というのも、オリジナルローズは独自で育種、生産するために出荷量が圧倒的に少ない点がネックでした。その分知れ渡るには時間がかかり、他の花に埋もれてしまっていたのだそう。
そこで、東京にも出荷の窓口を広げることに。すると、他のバラとは明らかに違うビジュアルがフラワーアーティストの目にとまり、業界内でじわじわと注目をされるように。またメディアでも取り上げられたことで、業界人のみならず一般客からも反響を呼ぶまでになりました。
そしてこの機を活かし、2010年ごろから一般客を対象に農園ツアーをスタート。健一さんがビジネスに掲げている「生産者と一般客を結ぶ」第一歩となりました。

“素人”だからこそできた、和ばらのトータルプロデュース
実は「和ばら」と呼んでいるバラには、「友禅」「てまり」「いろは」など、色、形、香りの違うさまざまな種類があり、これらを総合して「和ばら」という一つのブランドを確立しています。
健一さんは「和ばら」を一つのシリーズとして総合的に価値を上げながら、海外の市場へ展開したり、和ばらを使った加工商品を企画展開したり、一般客向けの新商品を開発・販売するなど、育種からPR、販売までをオールインワンでプロデュース。現在では経営直下にブランドディレクターを配置し、啓司さんの想いを国内外の顧客にむけてしっかりと届けるべく、全ての事柄を調整しています。
切り花ビジネスでは、このように育種者が自社の商品をブランディングし、様々に展開・PRすることは世界的にも極めてまれなことであり、本人いわく「日本では私たちしか手掛けていないと思う」と語ります。

しかし、業界で誰も思いつかなかったことを健一さんが企画できた理由は何だったのでしょうか。それは、切り花業界の固定観念にとらわれない「素人」だったから。彼は一度も園芸や農業に関する学問を学んだことはありません。
たとえばこんなエピソードが。日が経つにつれ花びらの色が変わっていくさまを、生産者のプロの啓司さんが「色が変わる花は劣化が目立つ」と考えるところを、健一さんは「色が変わるって面白いし、生きている感じがして美しいと思う」と違う見方を提案。業界の外から俯瞰して商品を見ることが、新たなビジネスチャンスを生み出すきっかけになっています。
2018年はさらなる飛躍へ
2006年に帰郷してから、健一さんは「品種を開発した背景や、父が思いを込めてつくってきた情熱を伝えるには、これまでの流通形態だけでなく、自分たちの“面白さ”をもっと広めるための手段があるはず」と感じていたそう。
そこで2016年には農園のコンセプトショップ「WABARA Cafe」を守山市内にオープン。和ばらを使ったメニューを提供したり 、和ばらをディスプレイ・販売することで、この花の魅力や、花のある暮らしを疑似的に体験してもらうことを目的としています。
このスタイルには、和ばらの生産者とブランドの認知度が向上するほか、和ばらの直販やBtoBビジネスへのフックにもなりうるという側面も。流通業者から市場へ売り出す方法と並行して行うことで、より収益を安定させることもできているのだそう。

さらに2017年4月には、びわ湖の辺りに待望の新農園「WABARA Farm」をオープン。“和ばら誕生の地”として農園ツアーの新たな拠点にするほか、食用バラの加工をスタートするなど、その試みはチャレンジ精神であふれています。

園芸のプロとして美しいバラを生み出す父親を、ビジネスの面から全力でサポートする息子。健一さんは家業を継ぐということを、このように話します。
「誰でもできるわけではありませんが、前提は“親のせい”にしないこと。やりたいかやりたくないか、を自分で決めることが一番大切です」
また家業を継ぐことは、これからの家の運命を決めるほどの影響力があるように思いがちですが、その点についても「うまくいくか、いかないかは私も正直わからないです。でもベストを尽くすことはできる。自分が良いと思うことをつきつめていけば、新たな出会いや視点が広がるし、そこから新たな展開があるはず」とも。
家業を継ぐか継がないかは“一か八か”のような賭けではなく、あくまで“自分がやりたい仕事だからやる”という純粋な視点で、家業を全うすることが大切と話してくれました。
親子で歩む二人三脚は、切り花業界を明るく盛り上げてくれるに違いありません。

國枝 健一(くにえだ けんいち)さん
バラ農家の長男。大学卒業後に実家に戻り、オリジナル品種「和ばら」のブランド展開を手掛ける。現在はブランドディレクターとともに、コンセプトカフェや農園見学の開催、海外展開の充実などさらなる発展に挑戦中。
https://www.facebook.com/rosefarmkeiji/
※國枝 啓司(くにえだ けいじ)さん
3代続くバラ農家の2代目。次男であり、和ばらの開発者。本人の人柄を表すような、穏やかで美しいバラの育種を得意とする。
生産のかたわら、2008年、2009年には日本5人のバラ職人に選出されるほどの作家でもある。皇太子殿下と雅子妃殿下のご成婚の際には、雅子妃殿下が直々にお選びになったばら「プリンセスマサコ」を献上したことも。
http://www.rosefarm-keiji.net/